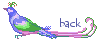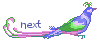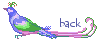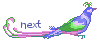彼の強引さが信じられなかった。
人を騙して呼び出しておきながら悪びれる様子もなく、当たり前のようにお昼に誘う。
けれど何より信じられないのは、結婚を控えていながら素性の知れない男と一緒にラーメンを食べている自分自身だった。
一体何をしているのだろう、私は。断ろうと思えばいくらでも断れたはずなのに、敢えてそれをせずにいる自分が不思議でしょうがなかった。
「腹減ってるんだろ。早く食べないと伸びちゃうぞ」
カウンター席のおかげで彼と向き合うことは避けられたが、隣に座っているというのもなにか落ち着かないものがあった。
湯気の立っている麺に息を吹きかけながら一口食べてみると、なるほど彼の言うとおりびっくりするくらいおいしいラーメンだった。
歯ごたえのいいシコシコした麺とまろやかさとコクのあるスープがからみあって、絶妙の味を出していた。前に食べた行列の出来るラーメン屋さんよりもおいしいかもしれない。
ちらりと隣を見ると、彼はもう食べ終わっていてナプキンで鼻の頭に吹き出した汗を拭っていた。
「早食いは体に悪いのよ」
私がそう言うと、彼は満足そうな顔でナプキンを丸めた。
「前にしてた仕事が昼飯食う時間もないくらい忙しかったから、早く食べるのが癖になってね。これでもゆっくりの方なんだ」
「どうして今の仕事を……ええと」
私は初めてそこで彼の名前を聞いていないことに気づいた。
「沢田恭介。前の仕事はクビになったんだ。大事な客を怒らせて、次の日にはクビ宣告」
「ご、ごめん」
「別にいいさ。特にやりたかった仕事ってわけじゃないし、成り行きで入ったみたいなもんだから。それより」
彼が続きを言うより早く私は答えた。
「川原侑子、って名前も知らないでどうやって電話してきたの?」
「ああ、北見さんの担当でこの間来てた客の中から勘で」
私はラーメンを食べるのも忘れて、呆れかえってしまった。
気を取り直して残りのラーメンに手をつけようとしたと同時に、携帯のバイブ音が微かに響いた。
「俺の方だ。ちょっと待ってて」
彼はそう言って携帯だけを持って店の外に出てしまった。
窓ガラス越しに彼が携帯に向かって謝っているのがわかる。どうやら仕事の電話らしい。
私がラーメンを食べ終わる頃に、彼はため息と共に戻ってきた。
「悪いけど戻らないと。またクビが飛びそうだ」
彼は皮肉っぽく笑うと、伝票を掴んだ。
「え、ちょっと。そんないきなり。それに割り勘にしてよ。ちょっと、沢田さん!」
こちらの話を聞こうともせずにレジに行こうとしている彼を私は慌てて引き止めた。
「恭介でいいよ。俺が誘ったんだから今日は俺が払う。用事あるんだったら、ここに」
言うが早いか沢田さんは、いや恭介さんは、一枚の紙きれをテーブルの上に置くとさっさと会計を済ませて店を出て行ってしまった。
取り残された私はのろのろと立ち上がると、やたらと威勢の良いおばちゃんの声に押されるようにして店を出た。
恭介さんが置いていった紙には、読解するのも困難な字で携帯の番号らしきものが書かれていた。
私は朝がひどく苦手だった。
低血圧のせいもあって、学生の頃から朝ほど苦戦するものはなかった。
目覚まし時計に何回も起こされ、やっと意識が自分の手元にふわふわ落ちてくるといった感じだ。それでも学生の頃に比べると、まだいくらかマシになったと自分では思う。
目覚まし時計だけで起きられるようになったのだから。
もっとまどろんでいたい気持ちをなんとかどかして、ベッドから起きあがる。
エメラルドグリーンのカーテンの隙間から、朝の日差しが溢れんばかりに差し込んでいた。
カーテンを半分だけ開けて、今日着ていく服をクローゼットの中から選び出す。
アパレル関係の、しかも洋服のデザインとなると自然と自分の着ていく服にも気を遣ってしまう。
一人暮らしを始めて今年で三年目。
今では一応の自炊とゴミ出しは出来るようになっている。ただ朝ご飯は時間的にも習慣的にも食べずに出ることにしている。
カレンダーで曜日を確認してから燃えるゴミを持って部屋を出る。
眩しすぎる日差しに目を細めながら、私は駅へと向かって歩き出した。
「ちょっと川原さんいいかしら?」
「はい」
「ここのフリルはもうちょっと多めにしてってこの間言ったでしょ。それからこっち。このプリーツの部分、もう少し何とかならない? このままじゃ、上の生地とつなげたときによれちゃうわよ」
目の前で私の作った服を細部までしっかりチェックしていくこの人は、デザイナーとしての腕は超一流と言ってもいいだろう。
有名デザイナーまであと一歩だ、とファッション誌でも書かれているだけあって三十代前半という若さで今の地位を得るだけのことはある。
ただどうしてもこの人とは馬が合わないのだ。もちろん尊敬もしているし、憧れのデザイナーなのだが、もっと根本的な、人間性を好きになれない。
「はい、すみませんでした。今日中には直しますので」
「急いでよ」
くるりと踵を返して歩いていく後ろ姿を見送ってから、私は聞こえないようにため息をついた。向こうでまたアシスタントに注文を付けているのが見える。
私は仕方なく、下半身だけのマネキンに着せた服からまち針をはずしていく。
今日も残業になりそうだ……。