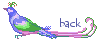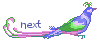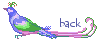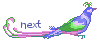ホテルの展望レストランには負けるかもしれないが、このレストランもなかなかのものだと思う。照明を落として雰囲気を出すのはもちろん、洒落たアンティークが品良く並べられている。窓際の席の私たちの横にはフクロウの置物がちょこんと立っているし、入り口にはイギリスの王宮にでも置いてありそうな陶器がずらりと並べられていた。
テーブルの真ん中に置いてあるランプもきっと高価なアンティークなのだろう。オレンジの灯がゆらゆらと揺れて、向かいに座っている修二さんの顔を照らしていた。
「侑子、あのさ……」
注文をしてからずっと黙っていた修二さんが、どこか落ち着かなさそうに言った。
「ん、なに?」
「いや……。やっぱりもう少し後にしよう」
「やだ、そこまで言ったなら言っちゃってよ。気になるじゃない」
修二さんは困ったように顎を掻きながら、おずおずと鞄から何かを取り出した。
「本当はもっと盛り上げてから渡そうと思ってたんだけど、このままじゃ飯の味もわからなくなりそうだから」
そう言って差し出したものは、青い箱だった。
思わずほころびそうになる顔をなんとか押しとどめて、私はそれを受け取った。
「まだ渡してなかっただろ」
ランプの光りを強気ではねかえすそれは、一目見ただけでもダイヤモンドだった。
「嬉しい……、ありがとう」
本当に嬉しかった。
プロポーズはされたものの、私はまだ婚約指輪を貰っていなかった。それでも修二さんの気持ちが本物だということはわかっていたし、わざわざ形にしなくても私は今のままで十分だと思っていた。
それなのにこうやっていざ貰ってみると、言葉が出なくなってしまうほど嬉しいのだ。
「あー、緊張した……」
プロポーズしたとき以上に緊張していたらしい修二さんは、大きく息を吐いた。
ふと思いついて私は訊いてみた。
「まさか、これ渡すために早く来たの?」
「あ、ばれたか。実は昨日から緊張しててさ、まるで学芸会を前日に控えた小学生みたいな気分だったよ」
あまりにも修二さんらしくて、私は笑いを堪えるのに必死だった。
「よし、これで心おきなく食べられる」
そう言って笑う修二さんに、私は心から微笑み返した。
それから私たちは妙に照れてしまって、まるでつきあい始めたばかりの中学生みたいにお互いの顔をちらちら見ながらディナーを終え、隣のホテルの展望ラウンジに移動した。
スツールに腰をおろし、私はモスコミュールを修二さんはウィスキーを水割りでそれぞれ頼んだ。
レストランでも飲んでいたので、ほどよくアルコールが体を巡っていく。
お酒にあまり強くない修二さんは、もう顔が真っ赤になっている。
「大丈夫? 今日は結構飲んでるけど」
「ああ。侑子は相変わらず強いな。羨ましい」
「私だってそこまで強いわけじゃないわよ」
ちょっとトイレ、と言って修二さんが行ってしまったので、手持ちぶさたになった私はバッグから鏡を取り出した。
夕食からまだ一回もお化粧直しをしていないことを思い出したのだ。どうやら私も相当舞い上がっているらしい。
鏡を取り出した拍子に、バッグから一枚の紙切れがはらりと落ちた。
こんなもの持っていたっけと思いながら、しゃがんでそれを拾った。二つ折りになった紙を何気なくひろげて、私は危うくまた落としそうになった。
そこには読みにくい字で、携帯の電話番号が書いてあったのだ。
ラーメン屋の帰り際に、恭介さんが半分置き逃げ状態で書いていったものだ。私はそのまますっかり忘れて、バッグに入れっぱなしにしていた。
あれから恭介さんから連絡はない。当たり前だ、こちらの番号を教えていないのだから。
今思えば恭介さんにはめられたような気がする。私が連絡をするかどうかで、自分に対する気持ちを測ろうとでもしているのではないか。
私が連絡をしなければ、このまま終わりだ。もしブライダル場で会ったとしても、連絡をしなかった以上は、向こうもなにもなかったように接するだろう。
破ってしまえ。心が警報を鳴らすかのように、心拍数が上がってくる。
でも何故か私の手は石のように動かない。左右の手を上下に引っ張るだけで簡単に破れるはずなのに、まるで金属でも破ろうとしているように、手は固まったままだ。
ふと背後に人の気配を感じて、私は後ろを振り返った。
修二さんがどこか険しい表情で立っていた。