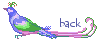大時計が鳴り響いた。
低く荘厳な音が城を石造りの古い街並みを包み込むように、正午の時を告げていた。
闘技場ほどはあろうかという広い広場では、午前の稽古を終えた見習い騎士達が顔を上気させてそれぞれの部屋へと散っていく。
簡素な鎧を身につけているだけだが、辺りには金属の擦れ合う音と剣の鍔鳴りが満ちていた。
ときに耳障りとなるその音も、今日は太陽の日差しを浴びて柔らかい音を放っている。
レシュタは稽古の時間が過ぎても帰ろうとしない見習い騎士たちにせがまれて、簡単な剣さばきを披露していた。
敵を模した人形相手にレイピアを突き刺していく。心臓に肺に、喉元に。
それは恐ろしいまでの正確さで人形の体を貫き、そばで見ている見習い騎士たちに感嘆の声を上げさせた。
見習い騎士たちはその冴え渡る技のひとつまみでも会得しようと、必死になって目を大きく開き、神経を尖らせている。
いつものことだ。
レシュタは特別な騎士だった。七歳のときに当時騎士長だったグレソンの目に留まり、騎士としての職業教育を始められた。
基礎体力作りとしてひたすら走ったり、よじ登ったりから始まり、泳ぎ、乗馬、剣術、槍術を毎日朝から晩までみっちり教え込まれた。
十二歳になるとそれらに加え、騎士のたしなみとして客や王族の接待や護衛なども学ばねばならなかった。
人にはそれぞれ得意分野というものがある。騎士のたしなみが得意な者もいれば、剣技や乗馬が得意な者もいる。そして滅多にいないのが文武両断の騎士。
レシュタはその文武両道の騎士だったのだ。
剣を握らせれば年上の先輩騎士も技で負かし、王族の接待をさせれば幼いながらにも身分をわきまえた言動で王族や貴族を驚かせた。
まるで騎士になるべくして生まれてきたと言っても過言ではないほどに、レシュタは騎士の素質を生まれ持っていたのだ。
そして何よりレシュタが特別なのは、女ということだった。
「相変わらずだな、レシュタ」
パチパチと拍手をしながら一人近づいてきた男に、周りにいた見習い騎士たちは一瞬怪訝そうに振り返った。
そして相手が騎士長であるヴァルだとわかると、慌てて一同は姿勢を正した。
レシュタはレイピアをさっと腰に差すと、軽くうつむく程度の礼をした。
「そのままで構わん」
ヴァルがそう言うと見習い騎士たちは少しだけ肩の力を抜いた。騎士長が稽古場に来るのは決して珍しいことではないが、それでも見習い騎士たちにとっては何度会っても慣れることのできるものではなかった。
「稽古時間が終わっても鍛錬に励むとは関心だ。たゆまず励むようにな」
ヴァルは見習い騎士たちを見回してから、レシュタに視線を送った。
「レシュタ、少し話がある。あとで騎士長室まで来てくれないか?」
その言葉にレシュタは一瞬だけ顔を曇らせた。
「わかりました。ではまた後ほど」
レシュタはそう言うとヴァルの視線から逃げるように、レイピアと傍らにある人形を片づけようとした。
「ああ! レシュタ様、片づけは私たちがやります」
「そうか、すまない。それでは頼んだぞ」
レシュタは見習い騎士に人形と練習用のレイピアを預けると、ヴァルに一礼をして稽古場を出て行った。
レシュタが騎士長室を訪ねたのは、すでに日が傾き始めた頃だった。
王族たちが住まう城内の一番端に位置している騎士兵舎は、暮れゆく太陽に照らされてほんのりと赤く染まっていた。
騎士兵舎の隣には王族の寝室や謁見室などのある居館が並び、反対側には礼拝堂が夕日を浴びて厳かに建っている。
夕刻のこの時間帯は騎士たちの半数以上が夕食を摂りにいっているため、騎士兵舎はひっそりとしている。レシュタの歩く靴音が、石の壁に反射して規則正しく響いた。
騎士長室は兵舎の一番奥まったところにある。
石壁に一定の距離ごとにくり抜かれた窓から、湿気を含んだ風がするりと侵入してはレシュタの顔や髪を撫でていく。
レシュタは一番奥の部屋の前で立ち止まると、一つ小さな深呼吸をしてからゆっくりとノックした。
「入れ」
ヴァルの低い声がドアの向こうから聞こえ、レシュタは意を決してドアを開いた。
ヴァルは窓のそばに立っていた。
騎士長室に一つだけあるその窓はしっかりと閉められ、レシュタがドアを閉めるとそこは二人しかいない密室となった。
「いきなり呼び出して悪かったな。こうでもしないと二人きりになれないもんでね」
「いえ。ご用件は何でしょう?」
レシュタは微かに張りつめた声を出した。ヴァルはそんな彼女を見やると、表情を緩めながら言った。
「なあ、ここは俺たちだけだぞ。そんな他人行儀に話すなよ」
「ヴァル……、私は騎士なんだ」
「けど、その前に女だろ」
ヴァルはドアの前に突っ立っているレシュタに近づくと、そっと髪に触れた。レシュタの柔らかな金髪がヴァルの手からさらりと流れ落ちる。
「女の仕事は家を守り子どもを育てることか? それだけなのか?」
レシュタはヴァルの顔を真っ正面から見上げて言った。騎士として生きてきたレシュタの目には、けれど確かに女としての緋が灯っている。
「そうだ。それが女というものだろう。確かにレシュタの剣才を捨てるのは、騎士長として俺も惜しい。だが愛しい女を戦場になど立たせたくないんだ」
分かってくれ、とヴァルは懇願するように呟いた。
目の前で頭を下げんばかりにして話す男を、レシュタは愛情と同情の混ざった目で見つめた。
ぴっちり閉まった窓ガラスが、カタカタと鳴り始めた。どうやら風が出てきたようだ。
先ほどの湿った風といい、今夜は雨が降るかも知れないな。レシュタはそう思った。
レシュタとはヴァルは同期だった。
グレソン騎士長の目に留まって騎士の道に入ったレシュタとは違い、ヴァルは武門の誉れ高い貴族の出だった。
生まれたときから騎士になることが決まっていたヴァルは、幼い頃からその頭角を現していた。剣術の才はもちろんのこと、皆を束ねる統率力にも長けていた。
が、その分周囲からの風当たりも強かった。命令なら聞くが個人的に仲良くはなりたくない、そう言われて他の騎士見習いたちから疎まれていた。
除け者にされることはしょっちゅうだったし、卓越した剣術の腕も相まって練習相手さえ満足にいないほどだった。
そんな中、ヴァルが驚くくらい自然に普通に接してきてくれたのがレシュタだった。
当時十二才だった彼女は周りの騎士たちからの人望も厚かったが、ヴァルはどちらかと言うとレシュタのことを毛嫌いしていたのだ。
騎士の道に女が入るなんて騎士道に反する、幼いときはまだしも所詮女の力ではそのうちついて来られなくなるだろう、と。
けれどレシュタはヴァルの予想を反して、日増しに腕を上げていった。そしていつの間にか、ヴァルの良き練習相手となっていた。
そんな二人が距離を縮めていくのは時間の問題であり、必然的だったのかもしれない。
窓ガラスの向こうで雨音がし始めた。小雨が、沈黙してしまった二人に話す機会を与えるようにシトシトと囁いている。
レシュタはヴァルの視線を捉えると、
「私もヴァルとの結婚を望んでいる。その気持ちに嘘はない。だが同時に私は騎士の仕事が好きなんだ。孤児だった私を騎士として育ててくれたグレソン殿にも、もっと恩返しがしたい。ヴァルこそ、私の気持ちをわかってくれないのか……?」
真摯な眼差しを向けた。
「レシュタ。君の気持ちはよくわかる。けど考えても見てくれ。グレソン殿だって君が幸せになるなら、喜んでくれるさ。それにたとえ騎士をやめたとしても、ここで見習い騎士たちに稽古つけてくれて構わない。いや、むしろこちらから頼みたいくらいだ。レシュタが稽古をつけるようになってからは、見習い騎士たちのやる気も上がっている。たまに稽古をつけ、普段は家で過ごし、俺の帰りを子どもたちと一緒に待っている、それこそが女の幸せなんじゃないか?」
ヴァルは訴えかけるように一気に話した。
堂々巡りだった。
「……それなら、それが女の幸せと言うなら、私は女失格なのかもしれないな」
レシュタは寂しそうにぽつんとそう呟いた。
済まない、もう少し時間をくれ、レシュタはそう言うとくるりと踵を返して騎士長室を後にした。
一人残されたヴァルは為す術もなく彼女を見送ると、力が抜けたように椅子に倒れ込んだ。
その日、レシュタはいつも通り見習い騎士たちに稽古をつけていた。
「そう、その捻りを忘れるな」
レシュタは見習い騎士たちの腕を横から支え、自らが動かすことによって剣の動きを体に教えていた。まだ年端もいかない少年たちは、一生懸命にレシュタの言うとおりに腕を動かし、剣を振るった。
レシュタの稽古の人気は、この教え方と戦場での絶対的な強さだった。
「よし、シャスワーレとリルディ。おまえたち二人で練習試合をしてみろ。いいか、剣はゆっくり振るんだ、相手が動きを捉えられるようにな」
指名された二人は、緊張した面持ちでレシュタの前に進み出た。二人ともまだ十四歳という幼さだが、騎士としての腕前は見習い騎士たちの間でも一目置かれる存在だった。
剣を握り直し、忠実に飼い主の言いつけを守る忠犬のように、レシュタの合図をじっと待っている。
「構え!」
レシュタの鋭い声が飛び、練習試合とはいえ稽古場はしーんと静まりかえった。
たっぷり二秒置いてからレシュタは合図をしようと息を吸い込んだ。
その瞬間。
張りつめた空気をかき切るような声が、稽古場に響き渡った。
「レシュタ様ー! 敵襲ですっ。城門を突破され、すでに城内に敵が入り込んでいます」
「数は!」
「分かりません。どうやら暗殺部隊らしく、人数も侵入経路も分かっていません」
充分とはほど遠い情報だったが、見習い騎士たちを動揺させるには充分過ぎるくらいだった。
十二歳という最年少の見習い騎士たちがパニックに陥り、蜘蛛の子を散らすように逃げようとした。
それを止めようと先輩騎士たちが道をふさぐものだから、辺りは命令系統が混乱した普通の少年たちの集団になってしまった。
「落ち着けっ」
レシュタのよく通る声が見習い騎士たちの間を駆け抜けた。
「仮にもレスカル王国の見習い騎士が何という様だ! ここで慌てたら敵の思うつぼだぞ。隊ごとに分かれるんだ。隊長を先頭に二列縦隊」
普段と変わらぬ冷静なレシュタの様子に少し落ち着いたのか、見習い騎士たちは慌てながらもしっかりと隊ごとに並んだ。
「それでいい」
レシュタは冷静を装ってはいたが、内心は混乱していた。
城内まで暗殺者が入り込んでいるとなると、王族たちの命が危ない。騎士の役目は王族を守ることなのだから、任務の重要度としてはここを各隊長たちに任せ、レシュタは王族の護衛に回らなければいけないのだ。
けれど目の前で突然の奇襲に怯えきってしまっている見習い騎士たちを放り出すことは、レシュタにはできなかった。
「各隊長に告ぐ。ここは危険だ、皆を連れて騎士詰め所に戻れ。そこまで行けば駐在してる騎士たちがいる。くれぐれも混乱を起こしてくれるなよ。では、第一小隊、行けっ」
レシュタの声に弾かれたように第一小隊が列を成して駆けていく。続いて第二、第三。
レシュタは見習い騎士たちに気づかれないように抜け出すと、全速力で王族たちの部屋に向かった。
城内は怖ろしいほどの静けさに包まれていた。
どのドアもぴっちりと閉められ、ご丁寧に鍵までかかっている。侵入者に隠れる場所を与えないようにというヴァル考案の策が、見事なまでに成功していた。
戦争の絶えないレスカル王国だが、暗殺者が城まで入り込んだというのは前代未聞の出来事だった。にも関わらず、こうも早く対応ができるのはヴァルのおかげだった。
レシュタは静まりかえった通路をなるべく音を立てないように走っていた。音を立てればそれだけ敵にこちらの位置を教えることになり不利になってしまう。
そのとき、通路を右に曲がったところで剣の弾き合う音が聞こえた。
「リルディ!」
そこで暗殺者と戦っていたのは、騎士詰め所に避難したはずの見習い騎士だった。
リルディに返事をする余裕はないらしく、泣きべそをかきながら敵の攻撃をかろうじて剣で受け止めていた。
レシュタは腰に下げていた剣を目にも留まらぬ速さで抜くと、走り込みながら暗殺者の背を切りつけた。
が、それは寸でのところで敵のもう一本の刀身によって受け止められてしまった。
レシュタはすかさず剣を手元に引き寄せると、標的をレシュタに変えた暗殺者と対峙した。
「二刀流……。ガーレス国の者か」
レシュタは相手の正体を見抜くと同時に斬り込んだ。
勝負は一瞬だった。相手が突き出した剣を紙一重で避けると、レシュタは素早く剣を相手の喉元に刺し貫いた。
レシュタが剣を引き抜くと、暗殺者はぐしゃりとその場に倒れて絶命した。
レシュタは剣についた血を素振りで落として鞘にしまうと、リルディに視線を移した。
「どうしておまえがここにいる? 騎士詰め所に行けと命令したはずだが?」
リルディは尻餅をついた状態で腰を抜かしていた。レシュタの声で我に返ると、震える声で言った。
「す、すみません。僕、どうしても自分の腕を試してみたくて。どうせそんなに強くないだろうって……、そしたら」
レシュタは小さくため息をつくと、この血気盛んな少年をどうしたものか思案した。
「私はこれから王族の部屋に向かう。いいか、足手まといにならぬよう後ろからついてこい」
油断するなよ、とレシュタは念を押すと再び走り出した。
王族の部屋はここからそう遠くない。無事でいてくれ、レシュタは強くそう願った。
王族の部屋が近づくと、悲鳴と掛け声が入り交じって聞こえてきた。そこの角を曲がったすぐそこだ。
「まずい。もうここまで来てるらしい。リルディ、おまえはここで待っていろ」
「そんな! 僕も行きます。さっきは油断しちゃったけど、もう大丈夫ですっ」
「だめだっ。おまえはここにいるんだ。いいな?」
レシュタが強い口調で言うと、リルディは泣きそうな表情で頷いた。
「陛下たちには指一本触れさせん!」
レシュタが角を曲がって飛び出していくと、暗殺者の一人をヴァルが切り伏せたところだった。
暗殺者の数は……残り三人。対する騎士の数は負傷者を入れて三人だった。ヴァルの周りには騎士たちの死体が何体か転がっている。
「大丈夫かっ。私も加勢する」
レシュタは通路から暗殺者を挟み込むように立った。ヴァルの背後は王族たちの居る部屋。
「ありがたい。レシュタが入ってくれれば心強い」
暗殺者は攻勢が不利になったというのに、決して怯まぬ殺気を放っている。
どちらも手が出しにくい膠着状態となった。
先手を切ったのはレシュタとヴァルだった。見習い騎士時代のときに二人で編み出した技だった。目配せ――それと悟られないもの――をすると、一斉に一人の敵に斬りかかる。
標的外だった者たちがヴァルとレシュタの背中を狙う。けれどそれはくるりと身を返したレシュタたちの剣に弾かれ、敵の体の脇に一瞬の隙が生まれる。
もちろん二人がそれを見逃すはずもなく、鋭い剣が相手の脇を切り裂いた。
暗殺者たち三人は、微妙なタイミングのずれをみせながら床に倒れた。
「し、死んだんですか?」
ちゃっかり角からひょいと顔を出していたリルディが、恐る恐る訊いてきた。
「いや、生きているさ。こいつらからはたっぷり情報を聞き出さんとな」
ヴァルは倒れたやつの一人を持ち上げると、遅ればせながら駆けつけてきた騎士に引き渡した。
レシュタは部屋のドアを開けた。
中には王族たち全員が無事の様子で、安堵の表情を浮かべていた。
「レシュタ、ありがとう。ヴァルもよくここを守ってくれた。おまえたちには、いつも助けられている」
「いえ、陛下。それが私たち騎士の仕事ですよ」
ヴァルは陛下と二、三言かわすとレシュタの方に視線を送った。
視線の先のレシュタは、城の被害情報を続々と届けてくる騎士たちと深刻な顔つきで話し合っていた。
レシュタは視線を感じてヴァルの方を振り向いたが、彼はすでに背を向けていた。
その夜、レシュタは騎士長室を訪れていた。
この間来たときと違い、ヴァルの後ろにある窓は開け放たれていた。乾いた風が室内に流れ込み、机の上に置いてあった記録用紙がぺらぺらとめくれた。
ヴァルは浅く椅子に腰をかけ両肘を机についてレシュタを見上げている。
「そうか、被害は結構大きいな。まあ王族たちに大事がなかったのがせめてもの救いだ」
「ああ」
被害は甚大と言えば甚大だった。ガーレス国が放った暗殺者たちの数は十数人だったが、皆相当の手練れだったらしく、こちらの騎士も三十余名が死亡し、負傷者はかなりの数にのぼった。
「……これからはもっと激しくなるだろうな」
レシュタは窓の外を見やりながら呟いた。
「それは免れ得ないだろうさ。ここ十何年間なにもなかったことのほうが、よっぽど不思議なことなんだからな。向こうもいよいよ本気で侵攻戦に出てくるだろう」
ヴァルはそう言うと椅子から立ち上がり、レシュタの前に立った。
「これでわかっただろう」
問いかけてくる意味がわからず、レシュタは聞き返した。嫌な予感が背中をそろそろと這い上がってくる。
「騎士の仕事がいかに危険な仕事か、ということだ。特にレシュタ、君の場合は尚更だ。女の騎士となれば嫌でも敵の目に留まるだろう。しかも強いときた。格好の的じゃないか。いまこの瞬間だって狙われてるかもしれない。戦場に立ったらどうなる?」
ヴァルは外に声が聞こえるを恐れたのか、窓を閉めようとした。
「いや、開けておいてくれ」
レシュタは静かにそれを制止した。閉めきった部屋でヴァルと二人きりになるのが、堪らなく嫌だったのだ。
ヴァルは閉めかけていた窓を元に戻すと、レシュタの方に向き直った。
「君が戦場で敵兵と戦っているなんて……心配なんだっ。いくらレシュタが強くてもやられない保証なんかない。だから安全な家に居てほしいんだよ。君に傷ついて欲しくないんだ」
ヴァルの周りの温度が上昇していく。レシュタのところまで熱風が吹いてきそうだ。それに煽られるかのように、レシュタも言葉が口を飛び出していくのを止められなかった。
「それは私だって同じだ! 私だってヴァルが戦場に立てば心配だ。騎士長がどれだけ敵にとって憎い相手だか、ヴァルならわかるだろう。どうして私を対等に見てくれないのだ。私が女だからか?」
ヴァルはぐっと喉を鳴らして怯んだ。図星だったのだ。その様子にレシュタは心を乱した。
「やはりヴァルもそこらの男と変わらなかったということか。……結局ヴァルは自分が一番可愛いのだろう。私を失うのが怖いから、だから私の気持ちなど考えないんだ。逆の立場になって考えてみろ。私のことが心配だから私を家に置いておく? 結局は私を失って自分が傷つきたくないだけじゃないかっ」
ヴァルの瞳が激しく揺らめいた。プライドを、レシュタを想う気持ちを、傷つけたのだとレシュタは思った。それでもほとばしった言葉は、もう戻らない。
真っ直ぐにレシュタを見つめながら、ヴァルは体の芯がすうっと冷えていくのを感じた。
「それはどういう意味だ……。レシュタは、俺の君を想う心が偽りだと言っているのか。自分が一番の男だと言いたいのか?」
ヴァルは好きな女にここまで言わせている自分が、どうしようもなく情けなかった。
レシュタは愛している男をここまで追いつめてしまった自分に、どうしようもなく腹が立った。
風が入ってきた。冷たい風だった。それは二人の間を逃げるように吹いていく。紙がめくれる乾いた音が静まり返った室内に、寂しく響く。
二人はお互いの視線を受け止め、跳ね返していた。
「……わかった。君の言うとおりにしよう。レシュタはこれからも騎士を続けるといい」
ヴァルは冷たく言い放った。まるで言葉を雑巾のように投げつけたみたいだった。
「ただし俺は……君とは結婚できない」
レシュタはどうしてという言葉をぎりぎりで飲み込んだ。うっかり喋ると、余計な言葉がこぼれ落ちそうだった。
レシュタは返事をする代わりに、大きく頷いて見せた。
静かに踵を返しレシュタは騎士長室のドアに手をかけた。背後から追ってくる言葉はない。
レシュタは空気が流れるようにするりと部屋を出た。後からでてくる影はない。
騎士長室から続く通路はやけに寒く、どこまでも長かった。
レシュタは急ぎ足で通路を抜けると自室には戻らず、見回りの騎士たちが来ない古い渡り廊下に足を向けた。
一歩一歩に騎士としての威厳が溢れている。その確固たる歩き方が、壊れそうになる理性を何とか保たせていた。
渡り廊下はひっそりと静まりかえっている。今日の出来事のせいで警備にあたる騎士たちが増えたことも忘れるくらい、そこは人の気配がなかった。
新しい丈夫な渡り廊下ができてからは、こちらの古い方の使用頻度はめっきり減った。通ってもせいぜい月に一、二度だろう。
まるで時間に取り残された遺跡のように、ゆっくりと時を重ねている。
夜風にさらされているため石の壁は殊更冷たく、四角くくり抜かれた窓からは容赦なく風が吹き付けてくるが、レシュタは窓と窓に挟まれるようにして壁に寄りかかった。
明かり一つない廊下だが窓から差し込む月の光のおかげで暗くはない。
レシュタは腰に下げている剣を鞘ごと抜いた。カチャリといってはずれた騎士の誇りは、今日も何人もの命を奪い去った。
きっとこれからは何十人、もしかしたら何百人もの命を奪うことになるだろう。
頭の中でヴァルの言葉がリフレインし、瞼の裏にはヴァルの醒めた横顔がちらついた。
レシュタはそれらを振り払うように剣を胸元で握りしめると、上を仰いだ。石の天井。
無機質な石が、何十年もこの城を見守り続けた石が、暖かく囁いているような気がした。
「泣くものか、……私は騎士だ」
崩れ落ちそうなレシュタを支える志、騎士としての誇りに一粒の滴がこぼれた。
立て続けに二滴、三滴とこぼれては、剣の上で宝石のように輝いている。
音のない世界でレシュタは、騎士になって初めて涙を流した。
 参加作品
参加作品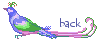

 参加作品
参加作品