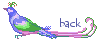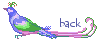僕は隣の住人の干してある服を見るのが好きだった。
下着を見るのが好き、という意味ではない。女の人の下着を見て喜ぶ趣味もないし、もちろん盗む気もない。
ただ春の夕方に、少し辺りが赤く染まり始めた時間に、まだ少し肌寒い風に吹かれてゆらゆら揺れている白いブラウスなんかが、僕の芸術的感覚をくすぐるのだ。
隣に住んでいる人と会ったことはないが、名前は知っている。
由里子。
前に彼女が友達と遅くまで飲んで騒いでいた時に友達から――あくまで騒いでいたのは「彼女の友達」で彼女ではない――大きな声でそう呼ばれていたのだ。
それ以来、僕の中では「隣の住人」から「ブラウスの由里子さん」にランクアップした。
僕の家は二階建て屋上付きの普通の一軒家。由里子さんは、五階建てのマンションの二階の一番端の部屋に住んでいる。
彼女の部屋は南向きで日当たりがいいので、大学に行く前にかならず毎日洗濯物を干して出掛けるのだ。
そしてその洗濯物というのが、ちょうど僕がベッドに転がってマンガを読んだりすると、窓からぴったりの位置で見える。目線を少し上にあげるだけで、由里子さんが干した桜色のブラウスや、しゃっきりとしたリクルート用のシャツがまるで鯉のぼりのように風に揺れて気持ちよさそうに空を泳いでいるのだ。
そこだけ風景写真から切り抜かれたようにぽっかりと浮き上がり、それを眺めている僕まで別世界に誘われていくようだった。
期末試験前のなにかと忙しい時だろうが、部活帰りのくったくたの時だろうと、僕が由理子さんの洗濯物を見なかった日はない。冗談ではなく、これを見るだけで気力も体力も全快してしまうのだ。
けれど最初こそは見るだけで幸せになれたのだが、毎日まいにち洗濯物を見ているうちに、それだけでは足りなくなってしまった。
そうするとあとはもうキリがなく広がっていく欲望の世界だ。
が、中学から高校二年の今に至るまで男子一色の男子校にいたせいで、僕にはまるっきり女性に対する免疫がない。口は悪いが根は良い僕の友達にこのことを言えば、やつのことだ。
当たって砕けろ! どうせ玉砕覚悟だろ。なに照れてんだよ。そんなOKの返事貰えるほどいい男じゃないこと生まれた時から気づいてるだろ。
と言われて終わりだろう。
それにこのどこか神秘的で切ないような風景を他のやつに教えるなんて、すごくもったいないことをしている気がして、親友だろうが、ましてや家族になんて言えるわけがなかった。
そんなことをしているうちに季節は、駆け足で春から夏に変わってしまった。
次の春が来る頃には、もしかしたら由理子さんはいないかもしれない。大学を卒業して就職すればもっと駅に近くて便利なところに引っ越してしまうかもしれないのだ。
けれど告白する勇気もチャンスもない。これでは堂々巡りではないか。
順ー、母さんちょっと駅前まで買い物に行ってくるから、留守番よろしくね。あ、それから時々お鍋の様子見といてね。
そう言い逃げをした母さんを自分の部屋の窓から見送った僕は、ここぞとばかりにエアコンの温度を下げた。冷たくて気持ちの良い風が顔の辺りに降りてくる。
夕方になっても夜になっても、気温は一向に下がらず、蒸し暑いことこの上ない。
今年は猛暑になるでしょうと言った気象庁の発表は見事に当たり、夏休みの部活動も中止になることがしばしばあった。今年はうちの学校でもついに熱中症の人が出てしまったのだ。
この暑さにはいい加減うんざりするが、夏休みの部活がなくなったことに関しては拍手を送りたい気分だった。この暑さの中、蒸しきった体育館の中でバスケをするなんてキチガイ沙汰だ。
ふと目の端に白い物体が横切った。
なんだろうと思い、僕はベッドから立ち上がり窓の外を覗いてみた。
僕の部屋の物干し竿に一枚の布が引っかかっている。
風に飛ばされたのだろうか。
隣の部屋は両親の寝室で、今日も僕のTシャツや親父のパンツなんかが干からびそうになりながら風にたなびいている。
窓を開けるとサウナのような空気が風に乗って冷え切った部屋の中に、勢いよく流れ込んできた。慌てて窓の縁に手をかけ、引っかかっている布を取って窓を閉める。
風になびいていたせいかハンカチくらいに見えた布は結構大きかった。
……フェイスタオルか?
広げて、硬直した。
それはタオルなんかではなく、キャミソールだった。
母さんが見栄を張ってこんな若い人用のキャミソールを買わない限り、うちの洗濯物にこんなものがあるはずがない。
だとすると……。
一瞬のうちに僕の頭の中で色々な考えが飛び交っていく。
そしてどう考え直しても一つの考えにぶち当たり、僕は改めてぎくりとした。
キャミソールを持っている手が心なしか震えている気がする。
冷静になれ、俺。
落ち着けって。そんなに握りしめてどうするんだ。シワになるだろ。
ひとまずキャミソールをベッドの上に置き、……思い直して机の上に置いた。
母さんは留守。由理子さんはさっき影が見えたから在宅。
僕はキャミソールと由理子さんの部屋を交互に見比べて、それから返しにいくかどうするかで二十分考え込むことになった。
それから二十分後、僕は由理子さんのマンションのエントランスホールに居た。
返しにくれば彼女と会話することが出来る。が、返してしまうのは正常な高校生男子にとっては、かなりの気力を要するものだった。
さすがに部屋まで行く気にはなれず、僕はエントランスホールにあるインターフォンを押した。
警備のしっかりしたマンションで、行きたくてもマンションの住人しか知らない暗証番号を押さない限り、僕の前に立ちはだかっているドアが開いてくれないのだ。
「はい、どちら様」
不意をつくように由理子さんの声がエントランスホールに響いた。
「あ、えっと。その……落とし物を」
上擦って少し掠れた自分の声を情けなく思いながらも、もう一度やり直せたとしてもきっと同じだと必死に言い聞かせて、言葉を繋いだ。
「洗濯物がうちに飛んできたみたいで」
いくらか冷静になった声にほっとして、相手の返事をじっと待つ。
「うそっ。やだ、ごめんなさい。すぐに取りに行きますんで、ちょっと待ってもらえますか?」
インターフォンを切る直前に由理子さんが、恥ずかしー、パンツ干してないよねぇ? と誰かに話しかける声が聞こえた。
その言葉に思わず僕まで赤くなってしまい、キャミソールの入った紙袋をぎゅっと握りしめた。
彼女は本当にすぐに降りてきた。
キャミソールの上に涼しそうな麻のシャツを羽織っている。下は昨日干してあった水色のジーンズに、海のような色のミュールをつっかけている。
顔はおそらくスッピンだと思うが、まじまじと見る余裕が今の僕には搾っても、ない。
僕から紙袋を受け取ると、由理子さんは本当に恥ずかしそうに何度も謝ってきた。
まさかいつでも飛ばしていいですよ、なんて言うわけにもいかず、僕はただ気にしないでくださいとバカの一つ覚えみたいにくり返した。
それじゃあと言って、またドアの向こうに消えていく由理子さんを見送りながら、僕は不思議な高揚感と軽い失望感を抱えながらしばらくその場に立ちつくしていた。
あれから八ヶ月が過ぎ、季節はまた春になった。
けれどもうあの洗濯物は揺れていない。
夕日を浴びて赤く染まりながらはためく洗濯物は、春の風が吹くと共にいなくなってしまった。
僕は遠くに見えるビル群の方に向かって、小さな声で告白した。