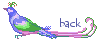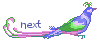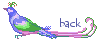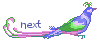ウェディングドレスの試着に行った日から、私たちはかれこれ二週間近く会えないでいた。
フィアンセである高橋修二は次の日から出張が入ってしまい、修二さんが出張から帰ったかと思うと、今度は私が下見出張に行かなくてはいけなくなってしまったのだ。
連絡こそは取っていたものの、内容は業務連絡みたいなものだった。
式場はこの間いったところに申し込むとか、引き出物はどうするとか、親族はどのくらい呼ぶかなど、間違っても甘い内容ではなかった。
私も修二さんのようにそういうことを決めている時間にも幸せを感じられるタイプなら良かったのだが、どちらかというと私は細々した決め事よりも、気持ちの確認をして欲しかった。
マリッジ・ブルー。
そんな言葉が頭をよぎっていく。
自分にはあり得ないことだと思っていた。マリッジ・ブルーなんてものは、幸せではいられないどこか不幸せなところがないと不安でしょうがない、そういう女がなるものだと思っていたのに。
下見出張の次の日は休み、とオフィスでは鉄則の決まりがある。
私もそれにならって今日は休みにさせてもらっているのだ。平日に休みがとれるなんて滅多にないことだからと思い切って外に繰り出したまでは良かったのだが、修二さんも呼び出す友達も仕事中、行く当ても特にないとなるとオフィスに近いこの並木道を散歩がてら、敵状視察するしか時間をつぶす方法を思いつかなかった。
腕時計の針は昼を過ぎようとしていた。
この時間なら昼休みのOLたちとぶつかることもなく、ランチがとれるかもしれない。
前から入ろうはいろうと思っていたが、なかなか機会がなくて入れなかった店にでも行ってみようか。特製のソースを使ったパスタに、セットで付いてくる自家製ドレッシングがたっぷりかかったヘルシーサラダ、それにデザートのティラミス。
そう思うと、急にお腹が減ってきた気がした。
店を目指して方向転換した瞬間、バッグの中の携帯が鳴った。
まさか仕事の呼び出し? 不安を感じつつ出てみると、知らない声が飛び込んできた。
「お仕事中、失礼致します。こちらはブライダルの者ですが、川原様でしょうか? 先日のプランとウェディングドレスのことでもう一度うかがいたいことがございますので、お時間のある日でもお越し頂きたいのですが」
丁寧な物言いとは裏腹に、無機質な感じのする声だった。きっとマニュアルでも読んでいるのだろう。
「それは今日でもよろしいですか?」
お昼を食べ損なうことになるが、空いている時間と言うと今日ぐらいしかない。
「ええ、もちろんです。それではお待ちしております」
電話を切ると、私は再び方向を変え駅に向かった。
プランについてのことだから修二さんにも連絡した方がいいのか迷ったが、結局止めることにした。
定期券を通して改札を抜けると、丁度ホームに電車が滑り込んでくるところだった。
携帯をバイブに設定し、私はドア脇の手摺りにもたれかかるように立った。
「あ、ちょっと待った。こっちこっち」
ブライダル場の入り口に入るなり、私は誰かに腕をつかまれた。
いきなりのことに思わず声を上げそうになりながらそちらを見ると、いつぞやの男がシニカルな笑みを浮かべていた。
「あ、あなた!」
「お越し頂き誠にありがとうございます」
「悪いけど、人と待ち合わせをしているの。担当の北見さんはどちらに?」
「北見さんなら今日は休み」
聞き捨てならない言葉に、私は思わず聞き返していた。
「じゃあ、私は誰に会いに来たのよ。電話をもらったから、こうして」
「俺に会いに来たの」
「は?」
「君に電話したのは俺だから」
彼は平然とそう言ってのけた。口の端をくっと持ち上げて笑いながら。
あまりのことに言葉を失っている私を彼は先日のようにまじまじと見つめると、
「もしかして喜んでるんじゃない?」
こともあろうかこう宣った。
「冗談でしょ。なんで私が喜ぶのよ」
体中の血が音を立てて、顔に集中してくる。真っ赤になったところを見られたくなくて、私は彼から顔を背けた。騙されたことへの怒りによるものなのか、からかわれたことにわざわざ反応してしまう自分への怒りなのかわからなかった。
「そんなにカリカリするなって。ちゃんと昼飯食った?」
「あなたのせいで食べ損ねたの」
はっとしたように彼が顔色を変えた。
「そうでしたか。それは失礼をいたしました。その件に関しましては、後ほどこちらから連絡させていただきますので」
彼が言い終わるか終わらないうちに、私たちの横を上司らしき人が不審顔で通り過ぎて行った。
上司がドアの向こうに消えるのを見届けてから、彼はふうっと肩の力を抜いた。
「危ない危ない。こんなとこに居たら、何個クビがあっても足りない」
彼はそう言うと、出口の方に歩いていってしまった。仕方なく私もその後を追う。
外に出ると、午後の日差しが柔らかく降り注いでいた。
駅から数分で辿り着くこのブライダル場は、周りの環境は最高の場所だった。結婚を控えた恋人たちが手を繋いで歩くにふさわしい雰囲気が、きれいに手入れされた植木や高級感のあるジュエリーショップから醸し出されていた。
大通りからはずれたところにあるため、車の騒音や排気ガスとは無縁で、駅と反対の方に進めば将来の理想になりそうなモデルハウスがあり、その隣には駅からも見える高層マンションが整列して建っている。
夜になればもっとムードのあることだろう。
「ほんと、よくこんな場所見つけたもんだよ」
彼は私の思っていることを見透かしたように言った。
「このブライダル場に来て、他のブライダル場見た日には幻滅だろうな。実際に一度断った客が次の週にまた来て、やっぱりここにしようなんてこと何度もあるしな」
どこか小馬鹿にした調子で彼は肩をすくめて、私を見た。
「昼飯まだなら丁度いいな。この先にうまいラーメン屋があるんだ」