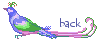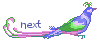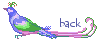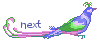美咲に舌を突き出して見せてから、私は化粧室の方に向かった。
相手はもちろん噂の人物、修二さん。
「はい、私」
自分の声が変わるのを感じた。
「僕。今いいかな、仕事中?」
小声で喋っているところを見ると、私より修二さんの方が今よくない状態らしい。
「私はお昼食べてるとこだから平気よ。それより修二さんの方がまずいんじゃない?」
「実はね、仕事中。でも上司が席をはずしてるから平気さ。それより今日は仕事、何時くらいに終わりそう?」
修二さんの潜めた声が耳に心地よく響く。
「今日は……」
まだ先生に言われたところを直していない。あれを直すのにも結構手間取りそうだし、それに下見出張の時の書類もまとめなければいけない。
「あ、いや。忙しいなら別にいいんだ」
修二さんは、私の沈黙をさり気ない断りと取ったらしく平然を装って言ってきた。けれどその声には明らかに残念そうな響きが混ざっている。
考えてみれば、彼と会うのは三週間ぶりだ。結婚を控えたカップルがこんなに会わないというのは良くないだろう。
マリッジ・ブルーなどとは言っていられない。
「今日は早く終わりそうよ。え? 大丈夫、無理なんてしてないから。うん、じゃあ八時にいつものレストランで」
嬉しそうな彼の声を聞き、彼が切ってから私も切った。思わず深いため息が漏れる。
化粧室の前で電話していたので、さっきからトイレの中でお化粧直しをしているOLたちの話し声が筒抜けだ。
電話を切ってから、まさか修二さんまで聞こえていないかと、心配になった。なにしろ内容が内容だった。よりによって、
「結婚前ってやたらと他の男が気にならない?」
なんて……。三週間会っていないだけでもダメージなのに、今の私たちにこれは冗談がきつすぎる。
笑い声と共に化粧室のドアが開いて、パウダーと香水の匂いが混ざったパワーの塊みたいな若いOLたちが出てきた。まるでビッグウェーブでも通り過ぎるように、私の横をすり抜けていく。
思わず彼女たちに舌打ちを送りそうになって、私は慌てて口を押さえた。
真っ暗な部屋に帰ってきたときの心細さには慣れた。つもりだったのに、こうしてマンションに帰ってきて自分の部屋だけ電気がついていないのを見上げると、どうしても居たたまれないような寂しさがこみ上げてくる。
重い足取りでエレベーターまで辿り着き、ボタンを押して待つこと一瞬。
もとから一階に止まっていたエレベーターのドアが開き、中から眩しいくらいの光りが広がってくる。その明かりにつられるようにしてエレベーターに乗り込み、三階で降りる。
鍵を差して部屋に入ると、予想以上に真っ暗な闇が待っていた。
私は洋服を着たまま、ベッドに思いっきり倒れ込んだ。
勢いで少し弾み、スプリングが軋む音が妙に辺りに響いた。電気を付けていないせいで余計に音が大きく聞こえた。
洋服がシワになることも気にせず、このまま眠ってしまえばどんなに楽かわからない。でもそんなことを出来るほど、私はナルシストでもなく馬鹿でもない。
のろのろと起きあがり電気をつける。辺りが一気に光りに包まれ、少しだけ人心地がついた。やはり明かりというのは、それだけで人を落ち着かせる力があるらしい。
着替えた洋服をハンガーにかけようと持ち上げた拍子に、ポケットに突っ込んだままだった携帯が音を立ててフローリングに落ちた。
拾い上げて着信を確認するが、表示されている文字は新着メッセージなし。
私は携帯を見つめながら、窓際のベッドに腰掛けた。
私が待ち合わせのレストランに着いたときには、彼はもう来ていた。
三十分近くも早くオフィスを出たから一時間くらい待つ覚悟でいたのに、私は店に入るなりウェイターにテーブルへと案内されたのだ。
「どうしたの?」
私は椅子に座るより先に思わずそう訊いてしまった。
「ん、何が?」
「来る時間、早すぎるわ。いつもは三十分くらい遅刻してくるのに」
「それは仕事がちょうど入るからだよ。僕はこれでも時間にきっちりしてる方なんだから。それにこうやって侑子と食事するのもひさしぶりだろ、つい張り切って会社を出たら予定以上に早く着いちゃったんだ」
彼は照れたように笑った。私の好きな笑い方だ。子犬よりは無垢でなく、大人よりは純情なこの笑顔に私は惚れたのかもしれない。