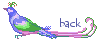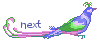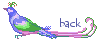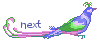私は思わず引きつりそうになる顔をなんとか押さえ込み、立ったまま何も言わない修二さんの様子をそれとなく探った。
「だ、大丈夫だった?」
「ああ」
私は手に持っていたメモをさり気なくバッグにしまった。
「もう一杯飲もうかな」
修二さんが空になったグラスをバーテンダーに渡した。
「じゃあ、私ももう一杯だけ」
同じ物をと言って渡すと、苦笑いとも同情ともつかない表情のバーテンダーと目が合った。
私たちの間にとろりと沈黙が流れ込んできた。だんだんと沈黙の密度が濃くなり、息をすることさえ苦しくなってくる気がする。
間に流れる空気に押しつぶされそうで、私は当たり障りのない話をしようとした。
「そういえば、」
「さっきのメモに書いてあったのって、携帯の番号だよな……?」
私の話を遮って、修二さんは言った。
ぎくりとした表情を慣れないポーカーフェイスで何とか隠す。
「うん、そうだけど」
「男の字だったよな。……こんなこと言いたくないけど、僕に隠してることない?」
別にやましいことなんてしていないのだから、言ってしまえば修二さんのことだ、きっとそれ以上は聞いてこないだろう。そもそも聞かれて困る話ではないじゃないか。
言ってしまえ。
「実は、さっきの……」
バーテンダーが狙ったようなタイミングで、お酒を二つカウンターに置いた。修二さんが仕方なさそうに私から視線を外し、二つのグラスを受け取る。
私は一口飲んで言葉を繋いだ。
「美咲の友達のなの。なんかその人、美咲のこと好きらしくて私からそれとなく聞いてくれないかって言われて、返事を聞いたらここに電話してくれって頼まれちゃって」
嘘をつく気なんてなかった。本当のことを言うつもりだった。
だが、口から出た言葉はいつ考えたかもわからないようなセリフだった。気が付いたらぺらぺらと喋っていたのだ。
「そう……」
一瞬だけ探るような目をした修二さんはどこか寂しそうにそう小さく呟くと、ウィスキーを割らずにストレートで飲んだ。
それきり喋らなくなってしまった修二さんは、杯だけを重ね続けた。
私はどうしていいかわからず、おろおろするばかりだ。いつもなら人懐こい彼の雰囲気が、信じられないほど近寄りがたいものになっている。
彼が何杯目かのおかわりをした。
さすがに心配になってきて声を掛けると、修二さんは少し焦点の定まらなくなった目で私を見て言った。
「……なあ侑子、信じていいんだよな? 侑子の言ってること、侑子のこと、信じていいんだよな。最近会わなかったのは、忙しかったからで他に……」
「そんな人、いないわ。私は修二さんが好きよ」
酔っている人に向かっていくら真剣に言っても、次の日には覚えていないかもしれない。それでも私は真剣に言わざるをえなかった。
修二さんのために、そして自分のために。
それから私は、泥酔してしまった修二さんをタクシーで家まで送り、そのまま待たせておいたタクシーに乗って自分のマンションに帰った。
金銭的に考えると修二さんのマンションからは電車で帰りたかったのだが、部屋で彼を介抱しているうちに終電の時間がきてしまったのだ。
それに今は混んでいる電車に乗りたくなかった。満員電車は朝のラッシュだけで十分だ。
タクシーに揺られながら、私はふいに泣きたくなった。感情の留め具が外れてしまったように、いきなり気持ちのコントロールができなくなる。
自然とあふれ出す涙を運転手に悟られないように、外を見るふりをしながら私はそっと涙を拭った。
なぜかいつもよりよそよそしく感じられる部屋に入るなり、私はベッドに腰をかけ、携帯を見つめた。
けれどそこに表示されているのは、新着メッセージなしの文字。
私は大きくため息をついた。もしかしたら目覚めた修二さんが電話かメールをくれるかも、と期待している自分が心底嫌になる。謝りのメールを送らないといけないのは、私ではないか。
普段、修二さんは自分が飲める量を知っているので、あそこまで泥酔することはない。あんなに酔った修二さんを見たのは始めてだった。
そして修二さんと喧嘩らしいことをしたのも始めてだったのだ。付き合ってから、私たちは喧嘩らしい喧嘩をしたことがなかった。いつもお互いの気持ちがわかっていたし、しっかり繋がっているという自信もあった。
今日のも喧嘩と呼べるようなものじゃないかもしれないが。
それでも私の中のお門違いの不安は消えてくれない。
再び携帯を開き、一番目に登録してある修二さんの番号まで辿り着く。けれど思い直して携帯を閉じた。あの様子ではもう今日は起きることはないだろう。
私はベッドから重い腰を上げて立ち、明日の用意をすることにした。何もしないでぼーっとしているのは、今の状態には一番良くないことだ。
明日着る洋服をクローゼットから取り出してベッドの隣に掛け、意味もなく化粧品を並べ替えてみる。
そしてバッグに手を伸ばし、私はそこで例のメモを思い出した。
こいつのせいで、と思ってみる。
私は雑に書かれた文字をそっと触ってみた。破きたくても破けなかった理由は、いったい何なのだろう。
いくら考えても出てきそうにない答えを探すのは、思った以上に疲れることだった。ゆうに十五分そのままメモを見つめていた私は、意を決してメモを丸めてゴミ箱に捨てた。乾いた紙の音が小さく響く。
これで全てが元通りになる、そしてこれで恭介さんとも終わりだ。
そう自分に言い聞かせるように小さな声で呟き、私は少し熱めに沸かしたお風呂に向かった。